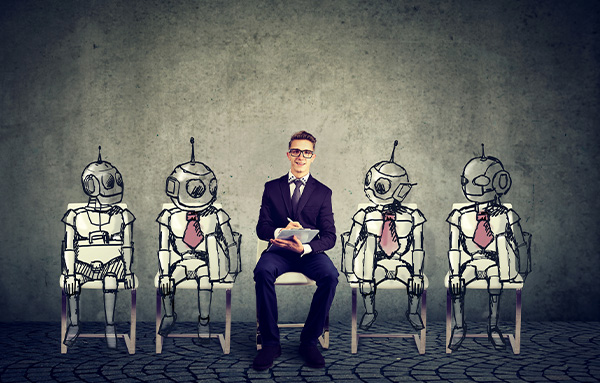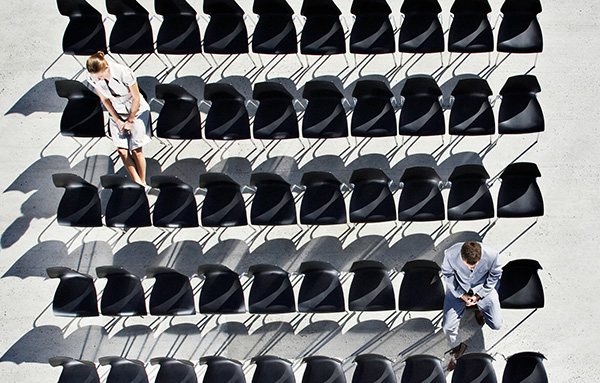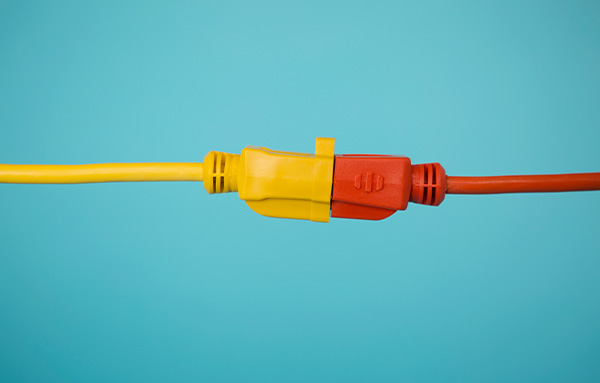-
太田 由紀
サイコム・ブレインズ株式会社
ファウンダー / プログラムディレクター 専任講師
価値観も人生のゴールも違う。でも、「この人のためなら」と思わせる

- よく「最近の若者は…」って言いますけど、実は江戸時代の人もそう言っていたらしいんです。本当に最近の若者が駄目であれば、人類はものすごく退化しているはずです。

- なるほど! 論理的に考えると確かにそうですね。

- やはり、今の若者は優秀なんですよ。大学生を見ているとそう思うんです。自分が大学生の頃に比べて、すごく真面目に勉強している。だた、優秀で真面目なんだけど、無駄がない。自分のために役に立つ、何らかの意味があると思わなければ動かない。だから、そういう賢い若者を動かせるだけの、ある種の蓋然性の高さみたいなものを提供してあげないといけない、という気がします。

- この点では、やはり上の世代とのギャップは多少ありそうですね。

-
あると思います。昔は価値を感じる対象が分かりやすかった。「いい車に乗る」とか「どこどこへ旅行にいく」とか、目に見える形のゴール設定をして価値を追求している人が多かったと思います。それもみんな同じような車を欲しがったり。今は一人ひとりが全く違う、自分が好きなものを持っていて、それぞれのベクトルが異なっているんです。たとえば「若者の車離れ」とよく言われますが、大学生の話を聞くとカーシェアをよく使うそうなんです。サークルのメンバーで移動するときに1日だけ車を借りるとか。今の大学生は普通にやっているんです。いろんな車に乗れるし、使いたいときだけの課金で済むし、所有するよりその方がいいんです。
そんな彼らをどうモチベートしたらいいのか、どんなインセンティブを示してあげたらいいのか、というのが昔の若者より複雑になっているのだと思います。おそらくそれは物質的なものではなく精神的なもの、やはり人の魅力というのはすごく大きい。「このリーダーのためなら」「このメンバーのためなら」と思わせることが重要なのではないでしょうか。おそらく、それができるかできないかで、リーダーの資質が変わってくると思います。

- 「この人のためなら」と思ってもらうためには、やはりコミュニケーションをして、知り合わないとどうしようもないですよね。

- そうですね。価値観を共有するというよりは、「自分はこういう価値観を持っているけど、あなたは違う価値観を持っていますよね」という相互理解でしょうか。もう一ついえることは、違う世代でも、自分と近い世代から始めるということでしょうか。50代の人はまず40代を味方に付ける。40代は身近な30代を味方に付ける。徐々に理解できる世代の幅を広げていく、という感じで。

- なるほど。いきなり離れたところから理解するのではなくて、近い世代からですね。

- 「こういう言葉が流行っているんでしょ?」みたいに突然若ぶろうとすると、浮いちゃうんですよね(笑)。ものすごく大きいギャップのところを思い切り大ジャンプするのではなくて、もう少しグラデーションをかけるように理解していくのがよいのではないでしょうか。

-
グラデーション…確かにそうかもしれませんね。国籍やジェンダーに関しても同じことかもしれません。女性で子供を育てながら働くなんて難しいだろうとか、かわいそうとか、けしからんとか。いくつかの感情をごちゃ混ぜにして持っている男性の方も結構多いんです。特に50代の方。ところが、ご自身のお嬢さんがご結婚されて、お子さんをお持ちになって働いている、となった瞬間に劇的に変わったりするんです。
世代間のギャップの話にしても、自分の身近な人、部下でも上司でも、隣の席の人でもいい。そういう身近な人たちと相互に理解する。そうすることで、ギャップはなくならないとしても、仕事でマイナスに働くようなことは少しずつ減るのかなと思います。