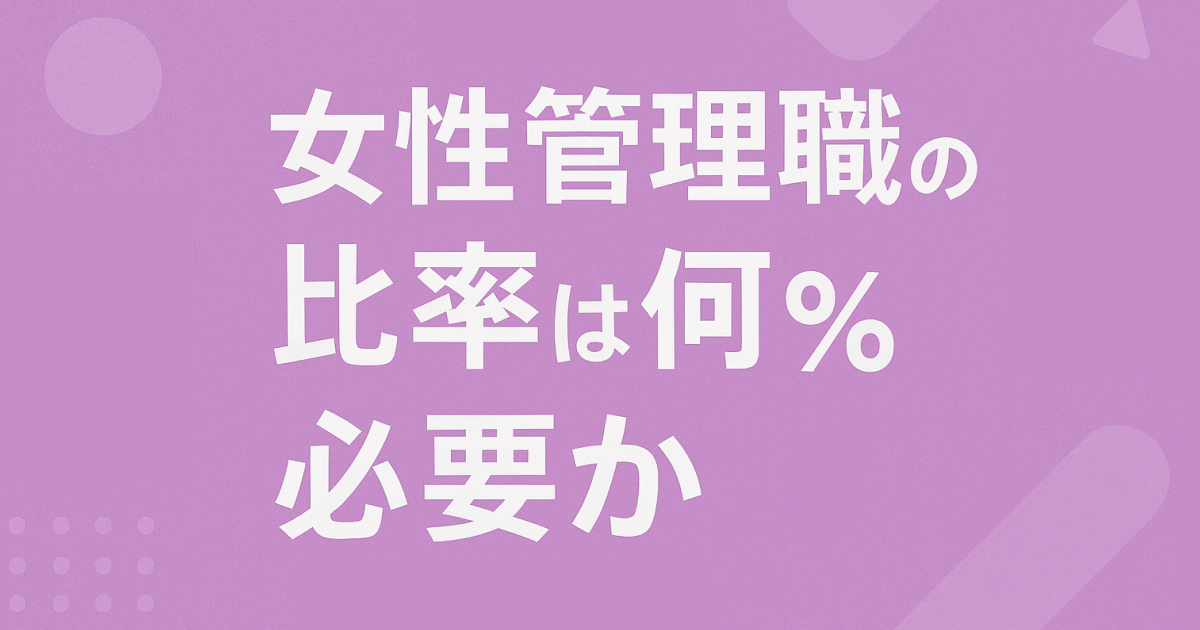
近年、企業経営において「多様性(ダイバーシティ)」の重要性が急速に高まっています。特に、上場企業をはじめとする大手企業にとっては、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)は単なる人事施策にとどまらず、経営戦略そのものと位置づけられるようになってきました。その象徴的な指標の一つが「女性管理職比率」です。日本政府が掲げる「女性管理職比率30%」という数値目標は、果たしてどのような意味を持ち、なぜその水準が求められているのでしょうか。本記事では、その根拠と重要性、企業にもたらすメリット、日本企業の現状、そして達成に向けた施策や事例、さらにはESGや持続可能な経営との関係まで、包括的に解説します。
- Index
女性管理職比率を30%にする根拠とその重要性
政府は「第5次男女共同参画基本計画」において、「2020年代のできるだけ早期に女性管理職比率を30%に引き上げる」という目標を掲げています。これは単なる政策的スローガンではなく、いくつかの学術的・国際的根拠に基づいた数値です。中でも注目されるのが「クリティカル・マス理論」です。これは、組織内の少数派が一定割合(一般的に30%程度)を超えることで、その存在が象徴的ではなく実質的な影響力を持つようになる、という社会心理学的理論です。つまり、女性管理職の割合が30%を超えて初めて、組織の意思決定や文化、制度に対して影響を及ぼすことが可能になるということです。
また、国際的にも30%というラインは一つの基準となっています。たとえばEU諸国では、上場企業に対して取締役会における女性比率を30~40%にすることを義務付ける動きが加速しています。日本も国際的な企業競争力を維持するためには、同様の水準を目指す必要があります。30%という数値は、経営における実効性とグローバルスタンダードの両面から導き出された、極めて現実的かつ戦略的な目標なのです。
女性管理職比率が高まることによる企業のメリット
女性管理職の登用は、単に「平等性」や「公正さ」を実現するだけではありません。女性管理職が組織決定や組織文化に対して影響力を及ぼすことは、企業にとっても非常に具体的なメリットがあります。
第一に、業績向上の可能性です。マッキンゼーの調査によると、経営陣のジェンダー多様性が高い企業は、財務的パフォーマンスが高い傾向にあるとされています。この調査では、カナダ、ラテンアメリカ、イギリス、アメリカの366社を対象に分析が行われ、性別多様性の上位25%に位置する企業は、業界の国内平均を上回る財務実績を持つ可能性が15%高いと報告されています。この研究結果は、性別多様性が企業の収益性にプラスの影響を与える可能性を示唆しています。これは相関関係を示すものであり、因果関係を証明するものではない、という見方もあるでしょう。
しかしながら、日本の科学技術・学術制作研究所の研究において、女性役員比率が上昇すると労働生産性が上昇すること、女性役員比率とビジネス・プロセス・イノベーション実現の間には相関性があることが確認されています。
つまり、多様な価値観や意思決定のアプローチが、イノベーションの源泉となり、より広範な市場ニーズに対応できる柔軟性を企業にもたらすといえます。
第二に、人材確保の観点です。働きやすい環境として評価される企業には、優秀な人材が集まりやすくなります。特にZ世代やミレニアル世代にとって、企業の価値観や社会的責任への取り組みは就職・転職時の重要な判断基準です。女性が管理職として活躍できる企業文化は、それ自体が強力な採用力となります。
さらに、社員のエンゲージメント向上にも寄与します。多様性が尊重される職場では、個々の従業員が自分らしく働けると感じやすくなり、定着率の改善、離職防止にもつながります。
ESG評価においては「S(社会)」における女性活躍が明確な評価指標となっており、MSCIなどが企業のダイバーシティをスコアに反映しています。
また、SDGs目標5「ジェンダー平等」は、ESG経営の根幹とされており、女性登用の進展が企業価値を高める要素となっています。
女性管理職が少ない日本企業の現状と課題
とはいえ、現実の日本企業において女性管理職比率は依然として低迷しています。厚生労働省の調査(2023年)によると、日本全体の女性管理職比率は約14.7%にとどまっており、OECD平均(約32%)と比べても大きく水をあけられています。G7諸国の中でも最下位という状況です。
この低迷の背景には、複数の構造的課題があります。まず、長時間労働・転勤を前提としたキャリアパスが女性の管理職登用を阻んでいます。また、出産・育児によるキャリアの中断が、昇進ルートからの離脱につながってしまうという現実もあります。
加えて、企業側にも課題があります。「女性は昇進を望まない」という先入観が根強く残っていたり、ロールモデルとなる女性管理職が少なかったりと、意識の壁も高いのが現状です。制度的な整備が進んでいても、それが運用されず”名ばかりの多様性”にとどまっているケースも少なくありません。
女性管理職が増えた企業が持続可能な成長を実現する理由
女性管理職の登用は、短期的なKPI達成のためだけではありません。それは企業が中長期的に持続可能な成長を遂げるための礎です。
まず、ESG投資との連動です。現在、世界中の機関投資家はESG(環境・社会・ガバナンス)を重視しており、その中でも「S=社会性」における多様性の確保は評価指標の一つとなっています。MSCIやFTSEなどの格付け会社は、取締役会の女性比率などを公開スコアとして扱い、資金調達や株価にも影響を与える状況です。
次に、SDGs(持続可能な開発目標)との整合性です。目標5「ジェンダー平等を実現しよう」は、企業活動のあらゆる領域に求められる行動指針です。女性の登用は、ESGやSDGsといった世界的枠組みに企業がどう応えるか、という観点からも評価されるのです。
さらに、社内文化の変革も進みます。女性管理職をはじめとした多様なリーダーが存在する企業では、従業員の発言の自由度や挑戦意欲が高まり、組織としての柔軟性と競争力が向上します。これは、単なるCSRではなく、明確な「経営上の強み」になり得るのです。
女性管理職比率30%を達成するための具体的な施策・取り組み事例
では、女性管理職比率30%という目標を達成するためには、どのような具体的な施策が必要なのでしょうか。
まず重要なのが「制度設計」です。柔軟な勤務体系(フレックスタイム制、在宅勤務制度など)の整備はもはや必須です。加えて、育児休業取得後のスムーズな職場復帰支援、時短勤務者への昇進機会の提供、男性の育児休業の取得促進など、出産・育児を理由にキャリアが停滞しない仕組みを整える必要があります。
次に求められるのが「人材育成の仕組み」です。既存の管理職育成プログラムに女性候補者をのせることだけでなく、女性自身が管理職を目指す意欲を高める環境づくりや、D&I推進をKPI化することにより、マネージャーに対して多様性実現の責任を明確にしたり、ロールモデル育成のためのメンタープログラムも有効です。
さらに、評価制度の見直しも重要です。成果に対する公平な評価、無意識バイアスの排除、性別を問わないリーダーシップ評価など、多角的な人事制度改革が求められています。
●花王株式会社
女性の昇進意欲を高めるために「女性リーダーシップ開発研修」を展開。参加者に自信と管理職への視野を広げる場を提供しており、同時に上司に対してもアンコンシャスバイアスの認知を促す研修を実施。これにより、上司と部下の双方向の意識改革を進め、昇進を後押しする風土形成に成功。
主な取り組み:
女性リーダー研修:リーダーとしてのスキル向上や視野を広げる機会として、外部団体主催の女性リーダー研修への派遣を行っています。
キャリCafé(Women’s Career Café):女性社員が前向きに「リーダーになりたい」と思える気づきを得て、自分らしいリーダー像について考える少人数座談会を実施しています。
女性リーダーキャリアパネルディスカッション:職種の異なる女性リーダーを招き、キャリアへの考えや両立の工夫、リーダーを担うことの面白さなどについて語るパネルディスカッションを開催しています。
出典:https://www.kao.com/jp/sustainability/walking-the-right-path/inclusive-diverse/dei/workplaces/womens-empowerment/
●三井住友海上火災保険株式会社:女性活躍推進のための意識改革と育成施策
女性が就業継続しやすい職場環境や両立支援制度の整備に取り組むとともに、働きがいや成長へのチャレンジを後押しするとともに、経験拡大のための機会提供や、管理職育成に向けた研修制度の拡充等を進めています。
主な取り組み:
プレマネジメント研修:若手・女性社員向けに、リーダーとしての役割を担うために必要な力を習得するプログラムを提供しています。
女性副部長・副支店長向け研修:副部支店長・副支店長を担う社員の「視座」を高め、物事の本質を捉えられる人財になることを目的とした育成プログラムを実施しています。
メンター制度:女性の組織長に、直属の上司とは異なるライン部長との1on1面談を定期的に実施し、経験の浅い組織長を育成、支援する制度を導入しています。
Re学:地元大学等が開講しているリカレント教育プログラムへの参加を支援し、転居転勤の少ない総合社員(エリア)の視野拡大とスキルアップを後押ししています。
出典:https://www.ms-ins.com/company/diversity/woman/
まとめ
2022年5月、企業が持続的成長を実現するための提言をまとめた「人材版伊藤レポート2.0」が策定され、その中であらためて、多様な専門性、経験、価値観を持った人材の登用ならびに活躍機会の提供、すなわち「知・経験のダイバーシティ」の推進が必要であることが示されました。
この「知・経験のダイバーシティ」推進の第一歩として、意思決定の場に女性を増やす、すなわち女性管理職を増やすことは企業にとって非常に有効な戦略であり、そのためには、女性を取り巻く組織の文化を変革すると同時に、女性自身が、恐れずにリーダーシップを発揮できるよう、育成面からサポートすることが最も重要です。
