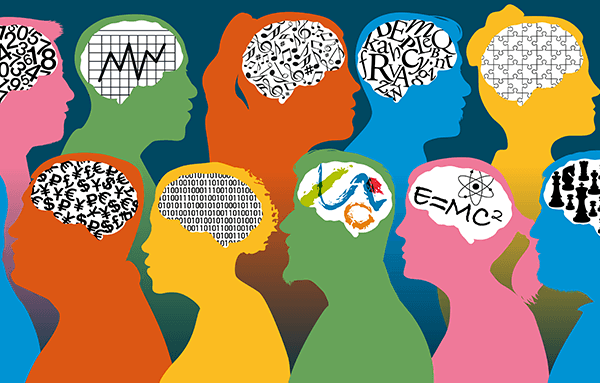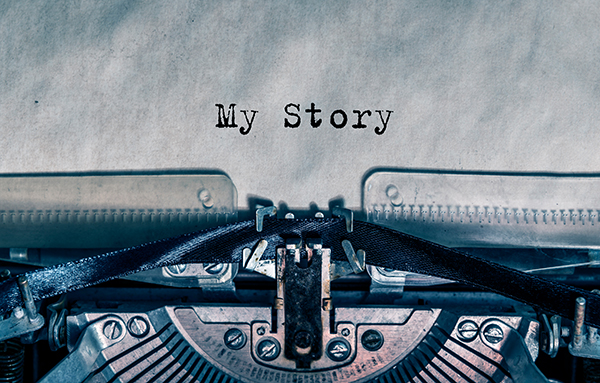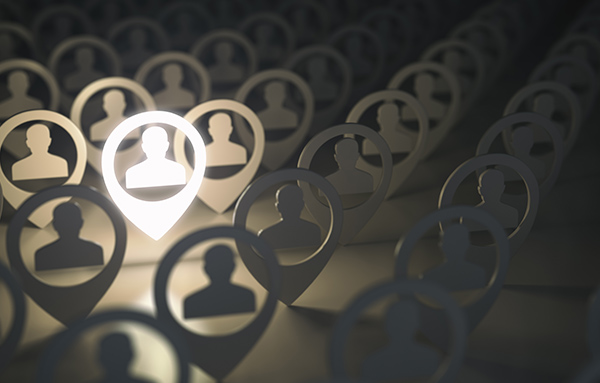-
江島 信之
サイコム・ブレインズ株式会社
取締役CSO
ともに働く他者との関係性、その中で自己理解を深める重要性は変わらない

- 組織の重要なポストに誰を抜てきするのか、候補者の中から選ぶときに、アセスメントによる客観的なデータを判断材料にしながらも、最終的にはマネジメントを含む関係者でタレントレビューをして結論を出します。その際にはマネジメントの考え、いうなれば「主観」、もっといえば「好き嫌い」が影響することも当然あります。100人いて100人が納得できるような評価なんてできないと思います。いくら設問設計を緻密にし、わかりやすいレポートに落とし込んでも、納得しない人は納得しない。要は、納得性をどれだけ高められるかが重要なんだと思います。結論に至るまでの議論を経ているからこそ、その結果をパワーを持って伝えられる。極論、アセスメントはその議論のためのツールでしかないのでは、と考えることもあります。

- 確かにそうですね。一方で、そのマネジメントの「主観」についても、一部の人の考えで組織の舵取りをするということ自体が難しい時代になってきています。シンギュラリティーの中で消滅する仕事の一つとして、マネジメントが挙げられているくらいですから。
-


- なるほど。組織自体のあり方がそこまで変わるというのは、考えもしなかった視点ですね。

- トップダウンの組織からホラクラシー、つまり役職や階級のないフラットな組織形態。あるいはコラボレーション型の組織になっていく。ブロックチェーンの仕組みを実際の組織に応用するDAO(Decentralized Autonomous Organization:自律分散型組織)という概念も出てきています。いずれにせよ、従来のマネジメントが機能せず、仕事も一つの組織の中だけでは完結しない。世の中が確実にそういう方向に向かっていると感じます。

- 仮にそうなったとしたら、360度フィードバックとかアセスメントって、今後どんな形になっていくのでしょうね。

- 組織形態の変化や技術の進化によって、情報の集め方は変わっていくのかもしれませんが、これまで以上に個人が、そして個人と個人の関係性をいかに円滑にしてパフォーマンスにつなげるかが重要になってくると思います。だから、「周囲からどう見られているか」とか、「一緒に働きやすいかどうか」とか、周囲との関連性を測っていくという方向性自体は、おそらく揺るぎないのではないかと思います。
-