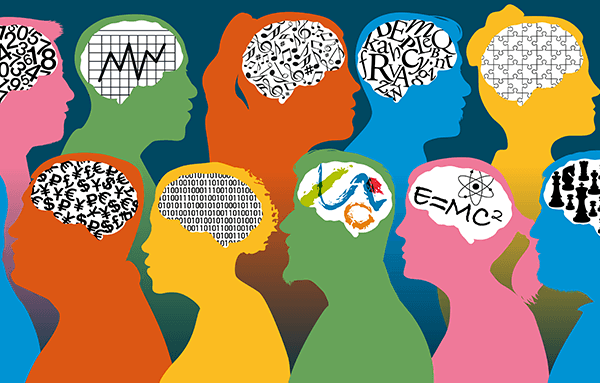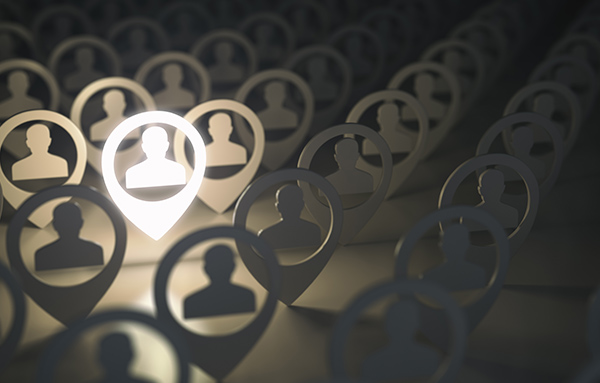-
齊藤 彩
サイコム・ブレインズ株式会社
ソリューションユニット コンサルタント
外せない特性と幅があってもよい特性。人材像をめぐる議論と気づきのプロセスにこそ価値がある

-
ある大手IT企業様で、部長・課長クラスを集めて「この部門で成果を出すにはどのような特性が重要なのか?」と、部門ごとで理想の管理職像を協議し、パフォーマンスモデルをつくるワークショップを行いました。
皆さんはじめは「絶対にこの特性は必要」「このぐらいの数値は必要」と厳格に各指標のスコアを決めていたんですね。ところが、あまり厳格に設定してしまうとそれに該当する人材がいない、ということに皆さん途中で気づかれます。その気づきを共有しながら協議をしていくと「意外と自由度を高く設定しても良いんじゃないか」「本当に重要な特性は実は1つや2つだけなんだ」といったことが可視化されていきます。

-
実は、そこがパフォーマンスモデルづくりの醍醐味で、つくるプロセス自体が学びになっています。ワークショップが、先入観や思い込みを外す気づきの場、発見の場になっている。協議の結果どのようなパフォーマンスモデルができたとしても、そこで皆で話したことに価値があるんですよ。

-
たとえば「この営業組織のマネジャーに求められるのは、数字の管理がきっちりしていることなのか、部下のモチベーションやエンゲージメントを高めることなのか」そういった色んな対話・議論に意味がありますよね。そして、パフォーマンスモデルというツールがなければ、そもそもこのような話し合い自体できないのではないかと思います。居酒屋で「うちのチームにはこういう人材がいないとダメなんだよね」などと言い合うことはあっても、会議室で膝を突き合わせて本気で必要な人材について討議するというのは、普段なかなかできないのではないでしょうか。

-
それが定量化のパワーかもしれませんね。空中戦になりがちなテーマも、数値に落とし込むことで話し合えるようになる。たとえば、コンピテンシーやリーダーシップといった言葉の捉え方は人によって違うけれど、数字の5は5だし、10は10です。定量化・データ化は「共通見解を得るためのツール」になるんです。


-
時々、お客様から、「パフォーマンスモデルを決めることは、人を型にはめることでは?」「これを使って私たちを選別するのか?」といった疑問をいただくこともありますね。福島さんなら、この疑問にどう答えますか?

-
PXTのパフォーマンスモデル設計には自由度があって、「この特性はしっかり持っている必要があるが、その他はそこまで重要じゃない」と重要度に濃淡をつけながら設計することができます。たとえば、経理としてのパフォーマンスモデルをつくるときは、「数的推理」「判断の客観性」は10寄りのスコアが必要だけど、「言語スキル」「社交性」などは広く幅を持たせて、色々な人がマッチしても良いというように、設計することもできます。
また、パフォーマンスモデルの役割のひとつに、人材の「育成の的を定める」というものがあります。ポジションの理想像を設けるからこそ、そのような人材を育成する課題を見極めることが可能になります。

-
先ほどのIT企業様のワークショップでも、自分たちで決めたパフォーマンスモデルと部長・課長ご自身のアセスメント結果とを比較していただき、「自部門で目指すべき姿や、自分自身が在りたい姿に近づくためにはどう行動すればよいか」と内省していただきました。また、同社の女性管理職の候補者にPXTを受けていただいたときには、結果を上司にもシェアし、候補者がすでに持っている強みとより強化すべきポイントを把握していただきました。今日、企業の人材育成に求められるスピードはどんどん上がっていて、育成期間も短くなっています。効率的な育成のためにも、パフォーマンスモデルを自社で議論し、育成の的を定める意味は大きいと思います。